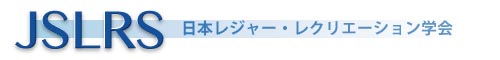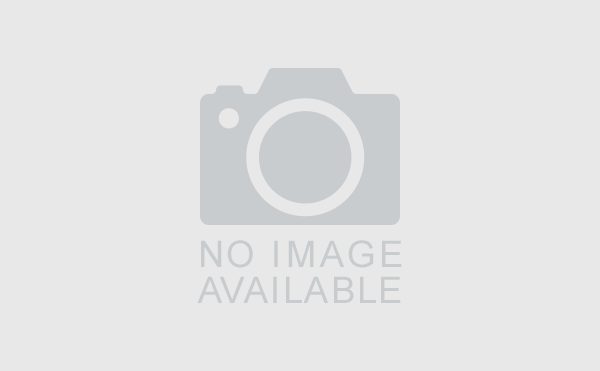鶯谷で教わったこと
昨年暮れ、久しぶりに御徒町の高架下にある飲食店を訪れたときの話です。コロナ前までは、友人の教え子にあたる大将に、ときどきゲストスピーカーとして授業に登場してもらっていました。「戦は陣取り、料理は段取り」という言葉が一般的なのかわかりませんが、複数の料理を食卓に同時に並べて楽しむためには、それぞれバラツキのある食材やメニューの調理時間と工程をオーガナイズする必要があるのは自明のことです。もちろん、仕事一般・家事全般同様なのですが、料理はその結果をその場でわかりやすく享受できるので、その話をお願いしていたという次第です。
また「水商売」という表現があるように、変化の早い世の中でどのような判断を下して対応しているのかについて伺うことも楽しみとしていました。そんなご縁で、時にはゼミ学生がアルバイトさせてもらうこともあります。実は今年も1人お世話になっているのですが、今回はなかなか苦戦中とのこと。ホールの仕事で接客もはじめてのようで、彼にとっては何もかも初めての体験です。各種作業の手際や接客対応の優先順位など注意されると、教えたはずのことも「習っていない」と言い張ったり、自分の趣味のことは良く話すが、お客様側の話となると途端に虚な眼差しで黙り込んでしまうようです。
確かに授業では、ヨゼフ・ピーパー氏の議論を持ち出して、現代社会における労働のかたち「一生懸命、がんばる、みんなのために」というスタイルを過大評価することは生きづらさを助長する、と教えました。そしてだからこそ、バランスを取るために「のんびり、時にはしゃぎながら、マイペースで過ごす」ことや出会いのための準備の大切さも伝えたはずなのです。しかしながら、その部分がすっかり彼の頭の中から抜け落ちているようです。とにかく空回りしてしまって全く楽しくなさそうなのです。そして「もうあそこでは働きたくない」と言い出す始末。彼は一体何に凝り固まってしまっているのでしょう。そこから抜け出すためにはどうしたら良いのでしょう。アドバイスできることはあるのでしょうか。
そんなことを思いながら、鶯谷にある完全紹介制で完全予約制の飲食店に「お呼ばれ」して出かけてきました。
店のドアを開けた瞬間に目に飛び込んできたのは、眩しいほどのネオンや電飾の間に所狭しと積まれたブリキのおもちゃ、東京タワーから太陽の塔まで、流行最先端なのか時代遅れなのだかわからないお土産品に類する世界中の置物、そして数えきれぬほど壁一面に貼られた大立者の千社札・・・。そう、18代目の中村勘三郎さんがお気に入りだったことでも有名な「あの店」です。そこは文字通り玩具箱をひっくり返したような「消費社会の夢のジオラマ」でした。そんな店内で披露された、数えで米寿に届かんとするご主人のMCと歌謡ショーは、「昭和の世界」の語り部が紡ぐ圧倒的なエンターテインメントでした。もはや店内にあるモノや音やおしゃべり以外のものが頭の中に入り込む余地はありませんでした。お店のドアから一歩踏み出したときに聞いたご主人のお見送りの言葉は、魔法の呪文のように響き、あとは足元を見ながら帰り道の歩を進めるだけで十分でした。余計なことを考える余裕や必要などありませんでした。夏の日の花火のあともこんな感じだったでしょうか。
あらためてレジャーについて教えることの難しさと目指すべき到達点のシンプルさについて思い知らされた次第です。