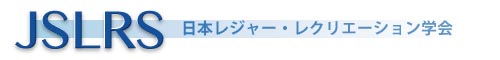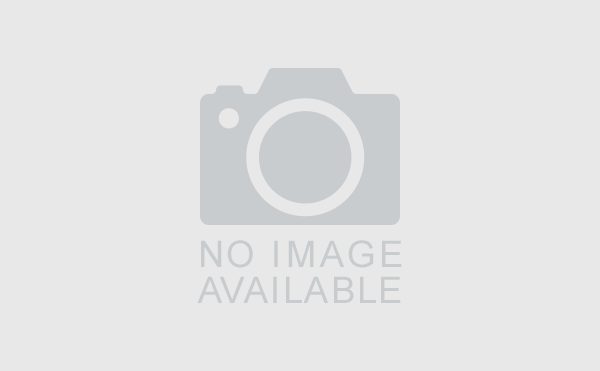大学にレクリエーション部を創設された先人に学ぶ ー創設の意義と実践活動への取り組みー
第79回 全国レクリエーション大会inあいち 研究フォーラム・セッション4 2025.11.1 レポート
講師:北翔大学特任教授・鹿屋体育大学名誉教授 川西正志 (中京大学体育会レクリエーション部 初代主将)
進行:仙台大学教授・日本生涯スポーツ学会会長 仲野隆士 (同上 第9代部員)
1972年(昭和47)4月、中京大学体育会の中にレクリエーション部が創設されました。これからの時代、競技生活だけでなく学生生活を楽しむという側面が必要と考えた教員から白羽の矢を向けられ説得された2名の学生が共鳴し、その2名でレクリエーション部を立ち上げました。その1人が初代レクリエーション部主将をなった川西先生でした。なぜ当該教員が大勢の学生の中から他でもない2名の学生に白羽の矢を当てたのか?…、それは「この2名が優秀で信頼に値し、必ずや部を創設し精力的に動いてくれるだろう」という確信があった事は想像に難くないでしょう。やがて後輩が入部していき当時は13名の部員で活動していたそうです。
当初は①地域子ども会からの依頼によるレクリエーション指導、②豊田市の体育課とコミットし、スタンツ教室という名での体操教室の指導、③福井県の教育委員会からの要請で青少年へのキャンプ指導(2週間)、④学内におけるレクリエーションイベントの企画と運営(バレーボールやサッカー大会、レクスキー等)を部の活動として展開しました。①の子ども会へのレク指導に向けては、自ら全国学校レクリエーションの研修会に参加され、日レク協会の指導者によるG・S・D指導の素晴らしさに衝撃を受け「ホンマモンの指導を理解すると共に、これなら自分でもやれそうと相性が一致した」という振り返りを離されました。周知の通り、レクリエーション指導・支援は独特の世界観があり、正に相性が合う・合わないがあります。レクリエーション部へは、その相性が合わないと入部することは無いとも言えます。③のキャンプ指導に向けては、自ら本場アメリカでのキャンプを2週間経験しにも行かれたそうです。そのように、「ホンマモン」とは何なのかを自ら実体験した上でコトを動かし進めていかれた点に初代主将を務められた川西先生の人となりを窺い知ることができました。その他お話の中で印象に残ったのは、「部員が前向きに取り組める部活動のプログラム作りに注力したこと」、「目標を立てPDCAサイクルで進めていったこと」、「やるからには効果を出さないといけないという信念で進めたこと」でした。
時は流れ、第9代のレクリエーション部の部員となり学生生活の大半をレクリエーション部で過ごした筆者の時代には、中京大学レクリエーション部の社会的な信頼が存在し、部活動の内容も全てレールが引かれたいました。当時の我々部員たちは、初代の苦労や開拓精神などを知る由もありませんでした。部員も増え、①②③④の内容は全てパワーアップしましたが、その根底には初代の「ホンマモン」の精神が存在し、先輩が後輩に知識や技術を指導し実践地と実践力を高めていく流れは脈々と受け継がれていきました。
初代から歴代のレクリエーション部の卒業生に目お転じれば、実にその6~7割が教員になり社会で活躍している事実は特筆に値するのではないでしょうか。教員を目指す人がレク部に入部するのか?、レク部に入部したから教員を目指すようになるのかは定かではありませんが、実見興味深いと感じています。
最後に、このセッションには歴代の中京大学レクリエーション部のOBやOGが参加してくれました。そして、現役の部員たちも参加してくれました。その部員たちに「あなたたちは何代目?」と聞いたところ、「私たちは3年生で第52代です。今の1年生は第54代になります」という事でした。初代が立ち上げたレクリエーション部が半世紀以上の歴史を刻んできたことに驚くばかりでした。
願わくば、日本全国の大学や専門学校などにレクリエーション部なる部活が創設されていく事を期待したいと思う次第です。